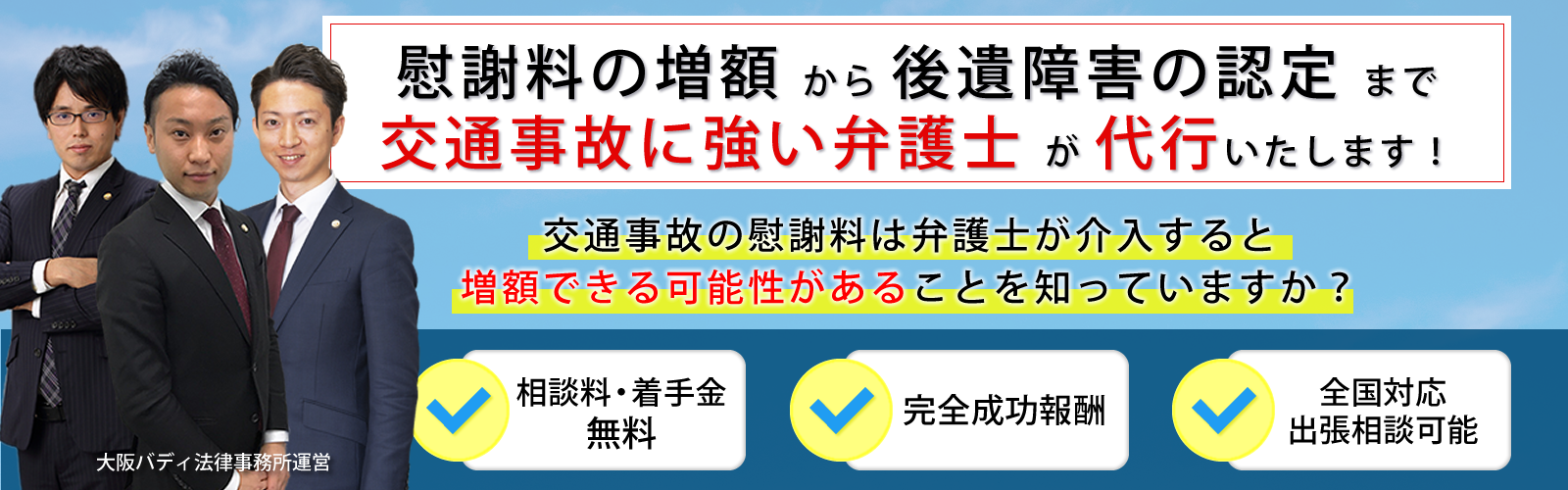1 はじめに
未成年のお子様が交通事故に遭われた場合、被害者の親が法定代理人として加害者の保険会社との対応をすることが多いと思います。
本稿では、未成年者のお子様が交通事故に遭われた場合における損害賠償実務のポイントを解説します。
2 子どもの被害事故の場合の損害賠償項目
被害者が未成年の場合に限りませんが、交通事故の損害賠償の場面では、治療費、通院交通費、慰謝料、後遺障害に関する損害など、様々な損害の項目が考えられます。
ここでは、損害項目のうち、特に未成年者が被害者となった場合に重要となる項目についてご説明します。
付添看護費
交通事故により、お子様が怪我を負い、入院を余儀なくされた場合、保護者が入院に付き添わなければならないこともあり、また、その後の通院においても保護者の付き添いが必要になります。
このように、子どもの入院・通院に保護者が付き添った場合、それに要した費用等が付添看護費という名目で損害賠償として認められる場合があります。ただし、親が子どもの入院や通院に付き添った場合に全てが損害賠償の対象になるということではありませんので、注意が必要です。
交通事故の裁判実務では、医師の指示があった場合や症状の内容・程度、被害者の年齢等から付添看護の必要が認められる場合に、付添看護費を損害項目として認められています。
被害者が幼児や児童であれば、一般に付添いの必要が高いといえますが、中学生以上であれば、単独でも通院をすることができると一般的に考えられています。そのため、医師の指示がない場合には、症状の内容や程度から、具体的に付添看護の必要性を判断する必要があります。
近親者による付添看護費は、入院の場合で1日当たり6000円、通院の場合で1日あたり3000円が目安とされ、具体的事情を考慮して、増額されることもあります。
休業損害
未成年のお子様がアルバイトをしているなどし、現に収入を得ている場合、交通事故によって休業が生じた際には、休業損害が認められる可能性があります。
また、未成年のお子様自身に収入がない場合でも、入通院に付き添うために親が仕事を休むことも考えられます。このように有職者が休業して子どもの入通院に付き添った場合には、上記の付添看護の必要性の観点から、親の休業損害と付添看護費とを比較して、その高い方が認められる可能性があります。
逸失利益
ⅰ 逸失利益とは
後遺障害が残ってしまった場合、その後遺障害が原因で事故前と同じように働くことができず、そのために収入が大きく減少してしまうことが考えられます。このような後遺障害の結果によって、本来得られたはずの収入(利益)が得られなくなる損害が、逸失利益として認められることがあります。
ⅱ まだ働いていない子どもの逸失利益は?
逸失利益とは、将来得られたはずの収入に対する賠償であり、一般に次のような計算式によって計算されます。
①基礎収入額 × ②労働能力の喪失率 × ③労働能力の喪失期間
なお、死亡事故の場合には、労働能力は100%失われる一方で、生存していればかかるはずの生活費を考慮して、②を「1-生活費控除率」とします。
では、まだ働いていない子どもの逸失利益はどのように考えるのでしょうか。
現に働いて給与を得ている人は、交通事故に遭う前の収入を基礎に考えますが、まだ働いていない子どもの場合は、逸失利益の算定基礎となる直近の収入額があるわけではありません。
このような場合でも、一定の年齢に達すると就労する通常ですから、男女別に賃金センサスにおける全年齢の労働者平均賃金を用いることとされています。被害者が大学生の場合には、大卒労働者の平均賃金が採用されるケースもあります。
なお、年少の女性については、女性労働者の平均賃金ではなく、全労働者(男女計)の平均賃金が採用されることがあります。
ⅲ 労働能力喪失期間は?
後遺障害とは、基本的に将来にわたって残存する症状ですので、これによるお仕事への影響についても定年まで及ぶというのが原則的な考え方です。現在の裁判実務では、症状固定時の年齢から67歳までの年数が原則的な労働能力の喪失期間とされています。
もっとも、まだ就労していない未成年者の場合、症状固定時から就職まで未就労の期間があることから、この期間を差し引きしなければなりません。
例えば、症状固定時15歳の中学生であれば、67歳に至るまでの年数は52年ですが、実際に就職するのが18歳からとすると、15歳から17歳までの3年間は減収を認める余地がありません。そこで、この場合には、52年から3年を控除した、49年間を労働能力喪失期間とすることになります(厳密には、52年に対応するライプニッツ係数から3年に対応するライプニッツ係数を控除します。)。
3 過失割合
過失割合とは
ここまでは、特に未成年者が被害者となった場合に重要となる損害項目について見てきました。交通事故の賠償問題では、損害項目以外に争点となることが多い問題として、過失割合があります。
「過失」とは、簡単に言えば、交通事故における当事者の不注意を意味します。交通事故の加害者と被害者との間で、当該交通事故の原因に対する不注意の程度に応じて賠償の負担を分担するという考え方を過失相殺といいます。その際の負担割合を「過失割合」といいます。
被害者にも過失が認められる場合、過失相殺は損害額全体に及ぶため、最終的な示談金額に大きく影響します。
過失割合の考え方
交通事故の実務では、「別冊判例タイムズ38 民事訴訟における過失相殺率の認定基準」という書籍に掲載されている類似・近接する事故態様の過失割合を参考にし、各事案における個別事情も考慮の上、具体的な過失割合を決定していくことになります。
基準となる過失割合については、被害者が大人であるか子どもであるかによって違いが生じる訳ではありません。
もっとも、この基準に沿って検討した場合に、被害者が「児童や幼児」であれば、過失割合を被害者に有利に修正する要素として主張することができます。これは、児童や幼児の場合、大人に比べて、一般に判断能力や行動能力が低いとされ、特に保護する要請が高いことから、過失割合を減算修正するという考えによるものです。被害者が「児童や幼児」である場合には、類型にもよりますが、大人が被害者である場合に比べ5~20%程度減算ことがあります。
なお、「児童」とは、6歳以上13歳未満の子どものことをいい、「幼児」とは、6歳未満の子どもをいいます。
親の過失が考慮されることもある
先にご説明したとおり、「過失」とは、当事者自身の不注意を問題としますが、過失相殺の場面では、被害者の社会生活上の落度ないし不注意を含む被害者の諸事情を考慮すべきとされ、いわゆる「被害者側の過失」として、もう少し広く解される場面があります。
児童・幼児は交通事故の場面において保護すべき要請が高い一方で、その親としても、そのような子どもの動静を見守り、交通事故に遭わないように注意・監督する義務があると考えられています。そのため、親がこのような義務を怠り、結果として子どもが交通事故に遭ってしまった場合には、親の不注意を加味して、「被害者側の過失」として判断されることがあります。
4 弁護士への依頼について
本稿でご説明したように、交通事故の被害者がお子様である場合には、それに応じて損害の考え方や項目を吟味しなければなりません。加害者側の保険会社が親切に説明してくれればいいのですが、必ずしも期待出来ません。
交通事故によりお子様が怪我をされた場合、ご両親としては、お子様のお怪我の心配や日々の付添いのためにお仕事に対しても支障がでることと思います。そのような状況で、加害者側の保険会社との交渉や電話対応も重なった場合には、その精神的な負担は計り知れません。
弁護士に依頼された場合、弁護士が被害者の代理人として窓口になることができます。ご両親はお子様の看病やお仕事に注力でき、ご両親がお子様に寄り添えることで、お子様のご不安を少しでも解消できることでしょう。
大阪バディ法律事務所では、お子様が交通事故に遭われた方のご負担・ご不安を解消するべく、全力でサポートいたします。